小泊十二景
荒川秀山(1800年都城に生まれ、のち都城明道館の先生となった。)が小泊湊の地を踏んだのは、文政十二年(1829年)ころの秋。秀山は小泊一帯を自分の足で歩き、目で確かめて、優れたこの地域の風景に感動し、その中から十二景を選定し、七言絶句の漢詩を詠んだものである。
(小泊村史 下巻より)
七ツ石(ななついし)

かいわんにおくをむすぶはこれたれがすまいなるぞ
結屋海湾是孰居
たんさとうがいにひぎよをつる
短蓑島外釣鯡漁
えぞいつぺきとおくにあらずといえども
蝦夷一碧雖非迥
ふなじなみたかくおもいしからずなり
舟路濤高意不如
海辺に小屋を建ててあるが、これはだれの家だろうか。短い蓑(みの)を着て島外の海に鯡(にしん)をとっている。蝦夷の島根は、海色みどりで遠くではないが、舟路の波が高くて思うようにはならない。
権現崎(ごんげんざき)

しやゆうりよううんだいいくそう
捨揖凌雲第幾層
すいへいうみにふしていきおいくずるるがごとし
翠屏俯海勢如崩
えぞぜつとうがいひんひろし
蝦夷絶島外浜大
はちめんらいちようもつともじようじようなり
八面来朝最上乗
散ったり集まったりする雲を凌(あお)ぐように、高く幾層楼のように高い、みどりの屏風のような岩が、海にかぶさるような姿で、今にもくずれるんではなかろうかと思われる格好だ。蝦夷が島の外海もだだっぴろい。四方からの船舶の来るに良いところである。
経島(きょうじま)

しんじんのれんせきそうめいにかさなる
神人輦石畳滄溟
よびなすおくせんいつさいのきよう
喚做億千一切経
いちいじこうたくをめぐらしてあらわる
一葦慈航廻棹見
ふうとうぼんをまなびえんれいにそびゆ
風濤学梵聳圓霊
神のつくった手本のような石が重なっている岩に砕ける波の音が、なんべんも一切経を唱えている。折りしも一小舟が衆生を済度(さいど)するが如く、棹(さお)をあやつって見えてきた。相変わらず高い風波が、梵(ぼん)経(きょう)を真似るかのように天に届いている。
羅漢石(らかんせき)

かいせきさくせいのだいらかん
怪石削成大羅漢
さんさしてうんぴようほんとうとともにす
参差雲表共奔騰
ごひやくきらいてじゆうろくとなすににたり
似慊五百為十六
ゆきあつしてとうがいなかばとうほうす
雪壓頭顎半倒崩
面白い格好の石と、削って造った石の大羅漢、入り交じって雲の上に駆ける馬といっしょのようだ。羅漢は五百だが、ここでは釈迦(しゃか)の命によって現世に正法を護持する十六羅漢でたくさんだというふうに見える。雪は深く羅漢の頭や顎(あご)を隠して半分の数のものが倒れていく。
姥石(うばいし)

うばいしくつきようちをはらいてわだかまる
姥石倔強祓地蟠
げんとしてさゆうにじそんをめぐらすがごとし
儼如左右繞児孫
そぞろにうたがうことうさんきようをくだるかと
坐疑孤棹下三峡
さんげつりようりようとしてやえんなく
山月寥々啼夜猿
姥石は剛直の貌(かお)をして災厄罪障を除くように神に祈っている。おごそかなさまをして、左右に子供や孫をしたがえているように見える。何となく一つ舟で中国の両岸の狭い川を下る気持ちになる。山に出た月は物静かで、どこかで猿が啼(な)いているように思われる。
辨天崎(べんてんざき)

ひりゆうぐうはんきゆういのわん
飛龍宮畔旧夷湾
なおおどろくがごとしべんろうのせきがんをひらきしを
猶愕辨郎闢石頑
かがえちぜんうんざいのはく
加賀越前運財舶
かぜをぼくしてこここのかんにはくす
ト風箇々泊斯間
飛龍神社のほとりの湾は、古い蝦夷の時代からのものだ。やはり驚くのは、弁財天がこの岩を切り開いたことだ。加賀、越前から舟が木材を積んで行く風の吹く模様で、舟が一隻また一隻とこの湾に泊まるのである。
稲荷堂(いなりどう)

すいそんさんかくよもよりきたるなし
水村山郭四無来
ほうふつとしてえいしゆうけいだいをめぐらす
![]()
えぞへいえんのけいをうつさんとほつす
欲冩蝦夷平遠景
かいわんいまだあかずがいかいをおさむ
海湾未飽納崖嵬
海村、農村の人だけで四方からは人が来ない。山はほのかとして仙人の住む瀛州(えいしゅう)の赤い玉をめぐらすようだ。蝦夷が島根のはるかに遠い景を写さんとした。海湾の潮はまだ引いたままだが、険しい崖は写っている。
青巖(あおいわ)

らんこうそめだすこれあおいわ
嵐光染出是青巖
てんろうのせきもんのけいなみなみならず
天老石門景不凡
もっともよしとうそんえんそうのゆうべ
最好冬邨塩竈夕
きえんかぜさからいてきはんをおくる
![]()
山気にあたる日光できれいな青岩、年月の経た風食の石門は実に美しい。ここの一番よいのは、冬村(ふゆべ)の塩を焼くかまどの烟(けむり)の立ちのぼる夕景である。ここの塩気の強い風が吹いて、港に帰る舟を送っている。
七瀧(ななつだき)

しちきゆうのけんせんせつらんをふく
七級懸泉噴雪瀾
ちほんせんしやしいざんをつんざく
![]()
ねがわくばはたらいらくたくせんがふでたらん
願将磊落謫仙筆
そそぐじんかんをしてもうこつをさむからしむと
灑使人間毛骨寒
七段の瀧は落下して真っ白い雪の波を吹いている。はげしく落ちること、矢を射るようで青山に地ひびきしている。こいねがわくば、勝(すぐ)れた詩人の筆で成った詩をもって、人々の骨の髄までぞっとするほど寒からしめたいものだ。
傾石(かたがりいし)

さていたんこかいはこなにかえる
![]()
かたがりいしのかいいなることもつともふぐんたり
傾石魁欹最不群
だいなるこくすうはあにざこくをとましめんや
大黒嵩豈富坐穀
いつすいのでるいくばくかのらんうん
一錐之出幾嵐雲
海岸に沿った漁家と樹木は粉のように小さく見える。断崖にそびえ立つ巨岩の風景も抜群である。大いなる黒岳はなんと稲の豊熟をもたらす山であることか。とがった頂上の近くには、いくばくかの嵐雲が起こっている。
燕崎(つばくらざき)

ようりゆうせきいでてじんきんをあらう
漾流石出濯塵襟
どうだいにしてあたかもどうしつのふかきがごとし
洞大恰如堂室探
いつたくひようぜんふなべりをうちいる
一棹瓢然鼓舷入
ときしらずぐんえんはしんにかまびすし
不時群燕噪波心
水がただよい流れ石が出て面白く欲気分を洗い去った。洞窓が大きく開いた広い部屋に似ている。一棹(ひとさお)さしてひっそり舷(ふなべり)をたたいて洞内に入った。不意を打たれて群(む)れ燕(つばめ)が波の上でさわぎ回った。
龍飛崎(たっぴざき)

げんびうしおたかくほうをとらえてかんなり
巖鼻潮高捕鮑閑
ぼういのきよほうがいひんのかん
防夷巨炮外浜間
しよへんのかせきはなれてがつす
渚邊化石離而合
きゆうばりゆうひしてなんぞかえらざる
厩馬龍飛何不還
巖(いわ)のある突端は潮高くはあるが、漁師はのんびり鮑(あわび)をとっている。洋夷防衛の大炮(たいほう)は外浜にある。渚にある化石は波に洗われ、ついたり離れたりする。武将の乗った馬は早く飛び渡って、どうしてそのまま帰らなかったのだろう。
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 水産商工観光課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-



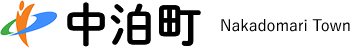
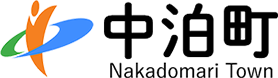
更新日:2022年04月01日